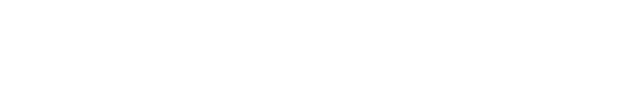消化器専門医、循環器専門医による診療
皆様こんにちは。
ニコークリニックは前院長田中裕幸医師により、1994年に開設されました。以来30年に渡り、地域に密着したクリニックとして、皆様に愛され続けてまいりました。
当院は消化器専門医、循環器専門医による診療、をキャッチコピーに、内科を中心とした幅広い疾患に対応できる診療所であると自負しております。丁寧な診察、時期を逸しない的確な専門医への紹介を心がけておりますので、かかりつけ医として、お気軽に安心して、当院を受診していただければと思います。
お知らせ
- 現在、お知らせはありません。
当院の特徴
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | / |
| 14:00~18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | / | / |
休診日 日曜・祝日
交通案内
〒8492201
佐賀県武雄市北方町志久1574
高野寺入口から1分
大きい地図はこちら
連携医療機関
当クリニックは、近隣の医療機関と緊密な診療連携を結んでいますので、入院や精密な検査が必要な際には、適切なタイミングでのご紹介が可能です。